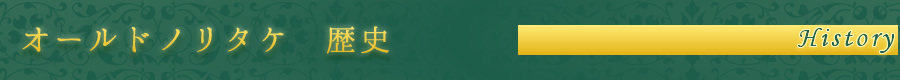ノリタケカンパニーの歴史
『オールドノリタケ』の歴史は、海外貿易を志した森村市左衛門が1876年(明治9年)東京に森村組を創業したことに端を発し、後年の太平洋戦争激化に伴い、食器の生産が中止される1943年(昭和18年)までの約60年間、森村組・日本陶器が世に送り出した陶磁器製品の歴史です。
森村組とモリムラブラザーズ
6代目森村市左衛門は、1839年(天保10年)江戸京橋にて武具商の長男として生まれました。1859年(安政6年)の日米修好通商条約による横浜港開港を機に「自由競争」の波が押し寄せたため、彼は、国内外での金銀対価の違いに起因する膨大な小判の海外流出を体験しました。当時、諸大名屋敷出入り商人であった市左衛門が、このことを中津藩士の福沢諭吉に話したところ、「外国人が持っていく金を取り戻すには、輸出貿易を行う他に道はない」と教えられ、市左衛門は自らがその先駆者となる決心をしたのです。
1866年(慶応2年)幕府が学術修業および貿易を目的とした海外渡航の許可を出したことを機に、15歳年下の弟、豊を呼び寄せました。そして、自身の貿易に対する理由と構想を伝えると、豊は、兄の描いた理想に共鳴し、国家のために役立つ貿易という仕事に、兄とともに身を挺することを決意しました。
幾つかの事業を経験したのち、市左衛門は東京銀座にモリムラテーラーという洋裁店を開きました。 一方、豊は慶応義塾に入学し、英語と商業を修得しました。そのころ、「ニューヨークで日本からの輸入品を扱う佐藤百太郎という人物が前途有望な青年を募っている」という話を諭吉から聞いたため、市左衛門は、豊の派遣を計画しました。そして蓄えた資金のすべてを投げ打ち、1876年(明治9年)洋裁店の2階を本社とする森村組を創業しました。同年3月、豊はオーシャニック号にて米国へと旅立ちました。市左衛門37歳・豊22歳。貿易を志して、実に17年後のことでありました。
ニューヨークに到着した豊は、イーストマンビジネスカレッジに通い、卒業後、佐藤らとニューヨークに「日の出商会」を設立しました。そこで雑貨商を開業し、東京の市左衛門に仕入れを依頼しました。
日本国内では市左衛門が、この年参加した義弟である大倉孫兵衛(大倉陶園創設者)とともに、工芸品、陶磁器、銅器、人形等、外国人に好まれそうな商品を買い集め、米国の豊へ送りました。しかし、開業当初は良かったものの、売り上げは、その後、伸び悩びました。さらに、佐藤らとの間で事業の考え方のずれもあって、豊は日の出商会を解消し、独立自営の精神で、1878年(明治11年)2人の日本人店員を雇い「日の出商会モリムラブラザーズ」を設立するに至りました。やがて、3年後の1881年(明治14年)には社名を「モリムラブラザーズ」と改名し、名実共にアメリカへの進出の第一歩を果たすこととなったのです。
一方、銀座の森村組も1885年(明治18年)には京橋区で敷地150坪の店舗を構えるなど、発展の途をたどりました。この当時の主な輸出商品は、錦絵、扇子、人形、漆器などの雑貨類と粟田焼、薩摩焼などの名古屋の問屋から仕入れた陶磁器でした。
1879年(明治12年)豊からの「片腕となる社員が必要」との要望で、福沢門下三羽がらす(残りの二人は犬養毅、尾崎行雄)の一人である村井保固(やすかた)を森村組に迎え入れ、営業基盤が強化されました。翌1880年、市左衛門は商業視察のため初めて渡米し、現地で日米の文化の違いを目の当たりにしました。早速、豊、村井とともに話し合った結果、将来の米国での事業として陶磁器販売が最も有望であると確信しました。翌年、市左衛門とともに一時帰国した豊は、日本各地を視察し、仕入れ商品を、新物の陶磁器と日本的な雑貨に絞ることとしました。
その後も業績は向上し、移転を重ね、飛躍的に発展していきました。また、モリムラブラザーズの新物陶磁器ビジネスも、インポートオーダー制(注文生産)を導入することでますます拡大していったのです。

洋風器製造法の修得と洋風画付け
森村組は、当初、名古屋で輸出陶磁器の画付け問屋を営んでいた瀧藤商店や友松商店から陶磁器製品を仕入れていましたが、今後は新物陶磁器を扱う商売がさらに有望になると考え、1883年(明治16年)頃、瀬戸の窯元加藤春光などに瀬戸生地の製造を依頼することにしました。
その後も森村組は、度重なる米国からの要求に応えるべく形状や品種の改良に努め、また生地仕入れの安定化を図る目的で、加藤春光窯をはじめ川本桝吉、高島徳松などの技量の優れた窯屋と専属契約を結ぶことにしました。画(え)付けに関しては、初期の頃には森村組が自ら画付け窯を築いて九谷地方から画工を招き、九谷絵・雪中模様の画付けをさせたこともありました。しかし、1884年(明治17年)頃には東京・名古屋に専属契約の画工場を持つようになり、瀬戸生地・フランスの白生地を仕入れて、九谷絵・錦手などの画付けをさせました。その後、1889年(明治22年)頃には、京都の石田佐太郎、名古屋の西郷久吉、東京の河原徳立・杉村作太郎・井口昇山・藤村興兵衛・足立清吉などが森村組の専属画工場として活躍しました。
1893年(明治26年)シカゴで開催された万国博覧会を視察した大倉孫兵衛は、ヨーロッパの先進国の陶磁器を見て、日本の製品が彩画・生地においてはるかに見劣りしていることを痛感し、洋風画の採用を決意しました。そこで、帰国の際、見本製品の他に、絵の具、絵筆、などの画付け道具類も購入し、各地の専属画工場に見本に倣った製品の試作を依頼しました。ところが、日本風の画付けにのみ専念していた画工たちにとって、洋風画付けの技法を習得するのは容易なことではなく、画工たちの説得と勧奨に多大なる苦心と努力を要しました。
明治中期には工業の都市集中化と大規模経営の傾向が顕著となり、日清戦争の終戦を契機とした急激な輸出需要の増加が起きたことから、1896〜1898年(明治29〜31年)にかけて森村組は名古屋の橦木(しゅもく)町に画工場を建設し、京都・名古屋・東京に分散していた画工場を集約しました。その後の1904年(明治37年)には錦陶組という画付け部門の統合体が組織され、各工場で見本製品を画付けしていた有能な画付け工員たちだけを分離し、画付け技術と意匠の向上を目的として見本工場を設置しました。錦陶組は1905年(明治38年)に真陶組と改称した後運営上の問題から解体し、一旦は旧体制に戻りましたが、1909年(明治42年)には錦窯組という画付け部門の統合組織として再生しました。
白生地の開発
1889年(明治22年)市左衛門と豊らは、パリの万国博覧会を視察した際、パリ郊外の製陶工場を見学しました。彼らはそこで、工場設備、製造、製品とすべての面での日本の陶磁器産業の遅れを痛感しました。その頃に森村組が仕入れていた生地は、脆弱でしかも純白ではなく、生産規模も小さな家内工業によるものでした。彼らは、このような瀬戸生地のみに頼った事業に限界を感じました。
1894年(明治27年)にニューヨークの大型専門店ヒギンス&サイターの経営者から、今後の事業において、下記の提言がありました。
(1)ディナーウェアに主体を置く。
(2)生地の色を純白なものにする。
この提言に応えるためには、まず製品の品質を向上させ、均一性を確保する必要がありました。そのためには、原料である坏土の改善が先決問題でした。白色硬質磁器の研究に関しては、金沢の工業学校で教師をしていた飛鳥井孝太郎を1896年(明治29年)に迎え入れ、翌1897年にヨーロッパに技術者として派遣しました。飛鳥井の帰国後、森村組は名古屋店の構内に研究所を設け、1899年(明治32年)から1902年(明治35年)の間、飛鳥井を白色硬質磁器生地製造の研究に携わらせました。その結果、天草陶石が質と埋蔵量において、きわめて有望であることが判りましたが、最大の課題である生地の改良については十分な成果が得られませんでした。そのようなとき、1901年(明治34年)にL&Eローゼンフェルド商会(英国・ロンドン)のB.ローゼンフェルド氏が、ニューヨークのモリムラブラザーズに来店しました。これを機にローゼンフェルド家所有のヴィクトリア製陶工場(オーストリア)を視察する承諾を取りつけ、1903年(明治36年)孫兵衛と飛鳥井は、ニューヨークの村井,大倉和親(かずちか)(孫兵衛の息子)と合流し、ヴィクトリア製陶工場で研究を行いました。そこで、生地改良に確信を持った一行は、最新式の製陶用諸機械を購入して帰国しました。一方,途中で別れた飛鳥井は独国・ベルリンの粘土工業化学研究所を訪れ、日本から持参した各種原料を使った調合を依頼しました。後に業界でいわれる「日陶3・3生地」はこのようにして開発されました。その結果、国内原料による白色磁器製造の道が開け、森村組の自社製造構想が実現したのです。しかし、この間の1899年(明治32年)には市左衛門の弟、豊が他界するという悲しい出来事がありました。豊は、享年46歳という若さでした。米国まで片道1ヶ月を要する時代に、豊の渡航回数は、実に、42回を数えたといいます。
日本陶器合名会社の誕生,名古屋製陶所,ディナーウェアの誕生,国内販売の開始
ヨーロッパから帰国した大倉孫兵衛と和親は、製陶工場の建設準備に着手しました。1904年(明治37年)1月1日森村組首脳6名(森村市左衛門、大倉孫兵衛、廣瀬實榮(さねよし)、村井保固、大倉和親(東洋陶器初代社長)、飛鳥井孝太郎)は、愛知県愛知郡鷹場村大字則武字向へ510番地に、日本陶器合名会社を創立しました。新会社では製造のみを行い、輸出販売の事業とは明確に切り離すべきとの考えから、その経営には市左衛門ではなく大倉孫兵衛・和親親子があたることになりました。最高責任者である社長には、優れた統率力・実行力・全幅の信頼・将来性から大倉和親が就任しました。和親29歳のときでした。 和親は、それまで勤めていたモリムラブラザーズを退社し、工場敷地の一角に住居を構え、工場建設に専任しました。工場建設は日露戦争の最中にも行われ、同年11月、製陶の生命ともいえる独国式窯場の火入れ式が行われるとともに、いよいよ日本陶器としての生産が始まりました。ここに、近代的企業意識に徹した西欧式製陶工場が出現しました。以後も工場建設は進行し、1906年(明治39年)には工場以外の寄宿舎・社宅・食堂など合計24棟の建物が建設され、工場従業員は1246名に達しました。1905年(明治38年)の日露戦争の勝利に伴い、輸出貿易も活発となりつつありました。そのような背景もあり、モリムラブラザーズからのインポートオーダーも急増し、日本陶器製ファンシーウェアの注文が森村組名古屋店に殺到しました。しかし、念願であるディナーセットのための純白白生地開発は思うように進展せず、1908年(明治41年)には組織運営の話し合いがもたれました。これ以後日本陶器は、今まで以上に生地製造にのみ専念し、森村組はその生地を購入・画付けしニューヨークのモリムラブラザーズへ輸出する分業体制が決まりました。すなわち日本陶器(生地製造)・錦窯組(画付け)・森村組(輸出)の3社によって運営されることとなったのです。また、この時点で正式に、森村市左衛門と村井保固は日本陶器の社員を辞しました。分業体制の決定にともない、日本陶器は純白白生地開発に専念しましたが、当初は歩留りの問題に再三悩まされました。しかし、改良に改良を重ね、ようやくヨーロッパ製品とほとんど遜色のない生地品質を確保できるようになりました。当時の主な製品は、花瓶、ボンボン入れ、鉢、化粧セットなどで、その後コーヒー茶碗、ティーポット、チョコレートポットなど製品の幅を広げていきました。

しかし、念願であるディナーウェア関しては、どうしても10インチ(25cm)のディナー皿が思うように製造出来ないという課題が残っていました。そこで、1909年(明治42年)、東京工業学校出身の江副孫右衛門が技師として加わり、飛鳥井とは異なる研究方法でこの問題に取り組むことになりました。 その結果、江副と飛鳥井両者の意見の対立が激しくなり、経営陣は重要な決断を迫られることになりました。結局、経営陣は、江副の意見を採用することとなり、飛鳥井は熟練の技師とともに退職しました。その直後に、彼は帝国製陶所(後の株式会社名古屋製陶所)を設立しました。飛鳥井の後任の百木三郎の下で技術主任となった江副を中心とした技術陣は、25cmのディナー皿完成に向けて研究を重ねることになり、大倉和親社長とともに、再び粘土工業化学研究所やビクトリア製陶工場に訪れました。ここで得た経験と生地製造責任者の伊勢本一郎の意見をヒントに、成型に改良を加えて、1913年(大正2年)に、ようやく念願のディナーセットが完成したのです。ヒギンス&サイターの経営者の提言から数えて実に20年、日本陶器の設立から10年の歳月が経過していました。日本最初のディナーセットの画柄には「セダン」という名が付けられ、初回20セットが輸出されました。以後、年々増加し、4年後には約40000セットが輸出されました。ディナーセットの受注拡大と並行してラーキン社(ニューヨーク)との商談があり、画柄「アゼレア」が採用され、この膨大な注文が、多品種少量生産のファンシーウェアから少品種大量生産のディナーウェアに生産方針を転換するきっかけともなりました。
一方、1908年(明治41年)には従来までの海外輸出に加えて、国内販売にも着手しました。当時の国内市場における洋風高級陶磁器の需要はきわめて少なく、英国・仏国からの輸入品が大半を占めていました。そこで日本陶器は、営業の目的を「陶器の製造及び販売」と改め、東京の三越、明治屋、大阪の草葉商店と販売契約を結び、翌1909年には内地販売部を設け、国内向け製品の専属画工場を開設しました。それ以降、日本陶器は、日本各地で開催された博覧会・展覧会などに積極的に出品し、ノリタケブランドの確立に努力しました。その甲斐あって1910年(明治43年)の宮内省への納入をはじめ、海軍省、また財界においては三井家・住友家などに製品を納めるようになりました。ホテル・レストラン関係への納品は1911年(明治44年)頃から始まり、帝国ホテル(東京)精養軒(東京)などで採用されていきました。とくに帝国ホテルでは、当初秋草模様の製品が使用されていましたが、フランク・ロイド・ライト氏のデザインした有名な日本陶器製水玉模様の製品に変更されました。
一般家庭へは、第1次世界大戦による国内景気の活況に後押しされる形で一部の家庭でコーヒーや紅茶を来客用に供することが流行し、需要が高まったことで、ようやく洋食器の国内販売も軌道に乗りはじめました。1916年(大正5年)には、内地販売部を分離独立することが決まり、日本陶器は合名会社日陶商会を、名古屋市西区に設立しました。同商会は、その後、1921年(大正10年)の日本陶器と東洋陶器の両者協定により、東洋陶器製品の販売も兼ねることになったことから日東陶器商会と改称し、本店を東京に移転しました。また、大阪市には関西陶器商会、名古屋市には中央陶磁器商会を開設し、国内における販売網を確立しました。
1919年(大正8年)、森村組と日本陶器が順調に業績を上げている中、森村組創設者である6代目森村市左衛門が他界しました。享年79歳でした。彼は、海外貿易事業の先駆者としてその名を残したとともに、多くの社会貢献事業でもその功績を称えられました。
日本陶器株式会社への改組,磁器和食器の誕生,火鉢
1908年(明治41年)に森村組と日本陶器の分業化が決定しましたが、事業の発展にともない、森村組は、1918年(大正7年)には株式会社森村組に改組しました。本店を日本橋区通り1丁目に置き、社長には7代目森村市左衛門(森村開作)が就任しました。それにともない、1920年(大正9年)にはニューヨークのモリムラブラザーズが吸収合弁され、商号は変わらないものの、実質的には(株)森村組のニューヨーク支店となりました。また、1917年(大正6年)には米国以外の地域への輸出業務を担当する会社として、森村商事株式会社が設立され、本店を(株)森村組と同じ住所に置き、社長には同じく7代目森村市左衛門が就任しました。1919年(大正8年)に同社は、名古屋市東区主税町に荷受所を設け、そこで荷受・検査・画付け業務も行っていました。
一方、日本陶器も、第1次世界大戦による世界的好況とディナーウェアの本格的生産の相乗効果で1917年(大正6年)には日本陶器株式会社と改組し、事業の拡充を目指しました。ディナーウェアの輸出先も、北米のみならず、ヨーロッパ諸国・南米・南アフリカ・オーストラリア・東南アジアと世界全域に広がり、1920年(大正9年)から始まる第1次世界大戦後の不況をも乗り越えました。この後しばらくは、日本陶器と名古屋製陶所のディナーウェアが、ノリタケチャイナとメイトーチャイナの名で世界中を席巻しました。
しかし、1929年(昭和4年)から始まった世界恐慌は日本陶器にも大きな影響を与えました。各国が自国産業を保護する政策を打ち出し、高関税による障壁を設けたため、日本陶器は企業の存亡が問われる厳しい状況に追い込まれました。そこで、日本陶器は経営基盤の再構築を試み、主力製品の転換(ファンシーウェアからディナーウェア)・米国以外の諸国への事業展開(海外特約店の設置)・国内市場への参入などの新たな施策を展開しました。1930年(昭和5年)には姉妹会社である東洋陶器と協議し、和食器などの国内向け製品の生産を始めました。磁器和食器分野へは1931年(昭和6年)から参入し、本格的生産は翌1932年に始まりました。また、火鉢などの和用小物が登場したのもこの頃からでした。
トンネル窯建設,ボーンチャイナの誕生,電灯笠
このような状況の中で日本陶器は、1933年(昭和8年)にトンネル窯7基の築造を中心とした工場の大改造に着手し始めました。トンネル窯の研究は1912年(明治45年)に遡りますが、当時においては多くの疑問点があり、建設が見送られていました。昭和に入り、ディナーウェアの需要拡大から徹底した合理化による量産体制が不可欠とされたので、工場大改造の構想が確立されました。そこで、トンネル窯が次々と建設され、合計素焼き用4基、本焼用3基の窯が完成しました。総工期約6年間を費やし、約15000坪に及ぶ建物の改築、諸設備の近代化が完成しました。

これまで、ファンシーウェア、ディナーウェアと世に多くの製品を送り出した日本陶器でしたが、さらなる発展を期するために、高級品としてどのような新製品を打ち出すべきかが議論されました。その結果、1932年(昭和7年)にそれまでの生地である硬質磁器とは異なる軟質磁器のボーンチャイナの開発を開始しました。主要原料の牛骨灰の研究をはじめ、様々な困難を克服して、やっと試作に成功し、1935年(昭和10年)からはようやく本格的生産を開始し、花瓶・置物などを生産しました。また、1938年(昭和13年)には大量のティーセットを米国に輸出し好評を博しました。
その後、日中戦争が激化するにつれて、1939年(昭和14年)10月には価格等統制令が施工され、金属を初めとする諸物資はすべて軍需が優先となりました。それに先立って1938年(昭和13年)には商工省令によって、金属製電灯笠の生産が禁止されました。これを機に金属代用品の研究が全国的に行われ、日本陶器では、磁器製電灯笠の生産が開始されました。
1939年(昭和14年)7月には米国が日米通商航海条約破棄を通告し、9月には第2次世界大戦が勃発しました。翌1940年の日独伊の3国軍事同盟締結により、日米の対立色が強まるなか、翌1941年の米国政府による在米日本資産の凍結で対米輸出は全面的に停止しました。1876年(明治9年)より米国で躍進したモリムラブラザーズはこのとき65年の歴史を閉じたのです。1941年(昭和16年)に始まった太平洋戦争が激化する1943年(昭和18年)に日本陶器は、管理工場としての指定を受け、磁器工場から研削砥石の生産工場となりました。この際、一部のボーンチャイナの生産ラインを残して日本陶器の磁器生産はすべて中止されました。このとき「オールドノリタケ」の約60年の歴史も終わりを告げました。